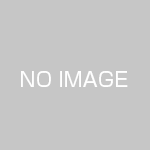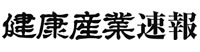中国広東省、東莞迎賓館で 日欧米からも有力企業集まる

第四回目となる国際食品由来ペプチド学術研究会(IACFP)が、中国食品発酵工業研究院(CNRIFFI)、中国保健協会などの主催で本日、中国広東省の東莞迎賓館(東莞市)で盛大に幕を開けた。CNRIFFIの董副院長は、「食品由来ペプチドに関する学術交流はもちろん、その産業化を通じて、世界に貢献していく」との意気込みを示した。

中国食品科学技術学会のシャオ秘書長は、中国のGDP(国内総生産)における食品産業の割合が重要な部分を占めていることを指摘し、「ペプチド分野における発展が、中国食品産業の将来にとって重要なモデルケースとなるだろう」とした。
今回の開催地となった東莞市は、食品由来ペプチドの産業化に力を入れており、同市科学技術協会の李主席は、「国家的イノベーションの先頭に立って、ペプチドの産業化に邁進する」ことが、「中国、ひいては世界への貢献となる」と指摘した。
中国保健協会 賈亞光秘書長 「ペプチドの機能性、これから」

中国保健協会の賈亞光・秘書長は、IACFP会場で健康産業新聞記者との単独取材に応じ、ペプチドに大きな将来性があるとの認識を語った。
「ペプチド自体は新しい素材ではないが、近年の研究により、その機能性が解明された。従来のタンパク質とアミノ酸に比べ、ペプチドはより早く吸収され、またさまざまな生理機能を有する。
日本の不二製油なども最近力を入れているが、まだまだ世界的に見れば新しい産業だ。中国の保健機能食品(ブルーハット)は1万5千ほどあるが、ペプチドを採用した商品は少ない。今後の研究が進むことで、健康への効果に関する新しい知見がさらに広がっていくだろう。」
第四回目となるIACFPには、中国全土から政府機関や有力企業が集まっているほか、日欧米からも有力企業が参加している。
日本からは、ワタミ、サラヤ、赤穂化成、アイワフーズ、エーザイフードケミカルなどの有力企業が参加するほか、東京大学の田之倉優教授、京都大学の佐藤健司教授、理化学研究所の小嶋聡一教授らが学術報告を行う。
欧米からも、DairyGold Food Ingredients (アイルランド)、B&D Nutrition(米国)、Jarrow Formulas(米国)などの有力企業のほか、ハーバード大学、カリフォルニア大学ロサンジェルス分校、ワーゲニンゲン大学(オランダ)などの研究者らが学術報告を行う。